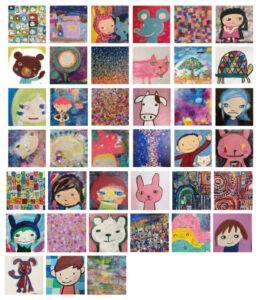前回のコラムでマイペースで過ごすことが社会にとってもよい効果を与えてる状態を「シナジー」と呼び、その状態を理想とするのがよいのではないかと書きました。
この方向性自体は特に間違ってないかなと思っているのですが、現実の状況を振り返ってみると、この状態を創るのはなかなか難しいことだと思っています。
僕は臨床家[りんしょうか]なので、絵空事のようなことはあまり言いたくありません。ただ、一方で目指すべき方向性というか理想がないと、どこに向かってサポートをしていけばよいのかがわからなくなるので、一定の方向が確認できたのはよかったと思っています。
では、実際の生活や仕事の中ではどのようにマイペースを大事にしていけるとよいのでしょうか?
僕は今のところ
①お互いのマイペースを確認する
②お互いのマイペースを調整する
の2点を意識しながら支援に取り組んでいます。
①お互いのマイペースを「確認する」
それぞれが自分にとって無理がないペースがどのくらいなのか、また今自分のペースで仕事や学業、生活がこなせているかどうかということを確認するという作業です。
心理士っぽくいうと「アセスメント」というところなのですが、客観的[きゃっかんてき]なところだけでなく、本人自身の主観的[しゅかんてき]な感覚がマイペースを図る上では重要な気がするので、本人がどう感じているかどうかも丁寧に確認しています。
客観的にというのは、割と心身の健康度合いから図ることが多く、食欲や睡眠時間、生活リズムなどのようなところから、気分の波や考え方がネガティブによってないか、またちゃんと休息もとれているかどうかなどから考えます。
また、主観的なところとしては以前書いたマイペースの基準(コラム④を参照)を本人に尋ねてみてどう感じるかなどを検討しています。
このように取り組むとだいたいの場合は「ちょっとマイペースとは言いきれないですね…」という話になることが多く、概[おおむ]ね、様々な理由からペースが乱されていたり、恒常的[こうじょうてき]に自分のペースを無視して活動していたりするので、その点を改めて見直していくという取り組みになりやすいです。
また「お互いに」と書いたのは、本人だけでなく、家族や周囲の関係者もサポート対象に入っているので、それぞれが無理なく取り組めているか、自分を犠牲[ぎせい]にして何かしようとしていないかということも合わせて検討するという意味合いがあります。なので、サポートをする支援者自身も「マイペースに取り組めているか」を自己点検してもらうことになります。
最近は支援者の育成にも関わることが多いので、その方が燃えつきたり、身体を壊したりしないようにするのも改めて大事だなぁと感じているので、上記のような視点を加えた方が良いだろうと思って、少し意識的に取り入れています。
②お互いのマイペースを「調整する」
「とはいえマイペースに過ごせないことも現実的にはあるだろう」というところから、マイペースの調整を考えるという取り組みをしています。
例えば試験前とか締め切り前だとかは、どうしてもそれに合わせた動き方になると思いますし、子育て中の方はどうしても子どもに合わせて動かざるを得ないということがあると思います。そんな中で「マイペースに過ごしてください」と伝えたら、それはむしろ相手を困らせることになるので、そんな押しつけがましいことは言えないな…と思っています。
では、そういった場合はどう考えるかというと「忙しい中でも自分なりに過ごせる時間をつくりましょう」と伝えて、忙しい中でのマイペースを考えるということをします。
具体としては、試験前で勉強をしっかりしないといけないなら、自分にとって取り組みやすい試験勉強のスケジュールを一緒に考えたり、仕事の納期が迫っている中でも身体を壊したら元も子もないので、どのくらいであればどうにかやれそうなのか、どのように休息を間に挟んでいくのか、あるいは自分だけでは無理だと思うものをどうやって他の人にお願いするか…等を検討します。
また、子育て中の方であれば、自分だけでは大変なので、周囲の人や専門家の人を頼ったり、レトルト食品や食洗器、予防接種[せっしゅ]のお知らせアプリなど様々なツールを活用して、自分でやることを少しでも減らすということを検討したりします。
このように取り組むと興味深いのは、大体の場合、話に出てくるのが「罪悪感[ざいあくかん]」に関することで「こんなに楽してしまってよいのか?」「こんなことお願いしてしまっていいのか?」など語られることが多くあります。
別に全然よいと思いますし、そもそも断られる前から遠慮しなくてもよいと思っているのですが、やはり自分でどうにかしないといけないと思ってしまうことがあるのだなと感じています。
そのような形で忙しい中でもマイペースを創っていき、そこを基準に日々の生活を見直していくような関わりをしていくと、ちょっとずつ落ち着いていくということがままあります。
特に発達特性のある方の支援をしていると、相手が子どもでも大人でも「ずいぶんと無理して周りに合わせてきたんだなぁ」ということがよくあるので、マイペースを意識してもらうとスッと落ち着かれることが経験上多くあります。
ただ、日々の相談の中では、本人も家族も、もはやなにがマイペースなのかよくわからなくなっていることがけっこうあります。学校や会社、世間の常識などを基準に考えて、それに合わせないといけないと強く思っていると、マイペースが見い出せず、ずっと辛いままでいることが多いと感じています。
もちろんマイペースであれば何でもやっていいわけでなく、暴言や暴力、その他自傷他害[じしょう たがい]になるようなことは、いくら本人が望んでいたとしても受け入れることは難しいかと思います。そのため、お互いにマイペースに過ごせるよう、どの程度は許容でき、どこからが難しいのかを調整するというのもマイペースを検討する上では大事だと思っています。
そんな感じで今はマイペースをテーマに日々相談や臨床をこなしており、いろいろな学びが蓄積[ちくせき]していっている最中です。次回はマイペースを調整していくうえで重要となってくる「対話」について、少し書いてみたいと思います。