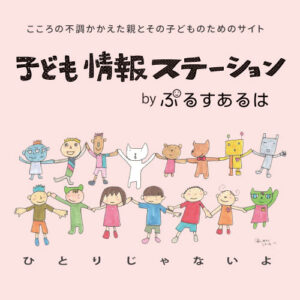僕は仕事やプライベートのことなどをいろいろとあれこれ考えて、だんだんと自分の考えがまとまらなくなると、心理学をはじめとする様々な理論や考え方などを調べて、整理しようとするクセがあります。
どうもそういう学び方が自分にとって学びやすいようで、このクセのおかげで知識が身についたり、臨床に知識を応用しやすかったりしています。こういった学び方が「構成主義的学習理論」と言われていることを最近教わり、学校とかだとアクティブラーニングとか、探求学習と呼ばれているそうです。
今まで仕事関連で「ケースワーク」とか「公衆衛生」とか「発達支援」などをとっかかりのキーワードとして調べることが多かったのですが、今回の「マイペース」は他と比べると難しさがありました。
理由としては「マイペース」をテーマとして心理臨床をしたり、調査研究をしたりということが、ほぼほぼされてないので、まず調べることが難しく、試しに論文検索で有名な「J-stage」というサイトで検索してみると、一番上にきたのが「マイペース酪農」という農法に関することした。これはこれで興味深かったのですが、ちょっと求めていることとちがうし、そもそも自分が何を求めて調べているのか曖昧[あいまい]なこともあって、どうしたものかと悩んでいました。
そんな時、別のことを調べている中でアブラハム・マズローについて知る機会があり、この方が提唱[ていしょう]している「シナジー」という考え方が僕の中で理想的なマイペースをイメージする上で、とてもしっくりくるところがありました。
アブラハム・マズローをご存じない方もいらっしゃるかと思うのですが、1900年代に活躍されたアメリカの心理学者で、日本だと「欲求の5段階」(よくピラミッド型で紹介されるやつ)などで知られる方になります。
そしてこの方が理想的な社会について説明している文献があるのですが、その中で理想的な社会を形成する上で「シナジー」という概念が大切であると説明しています。
「シナジー」という言葉は、時々ビジネス界隈[かいわい]などで使われる言葉で、「ある企業とある企業が合併して、お互いの良いところを活かしてシナジーを発揮[はっき]し…」などのように、相乗効果のような意味でつかわれることが多くあります。
ただ、マズローがいうシナジーは少し意味合いが異なり、その意味として、利他[りた]と利己[りこ]の双方が成り立っている状態であると説明しています。
つまり、自分のためにやっていたことがいつの間にか他の人や社会の役に立っていたり、誰かのためにと思ってやっていたことがいつの間にか自分にとっての生きがいになっていたり…というような状態がシナジーであり、良い社会を創る上ではこういった状態が理想であるということでした。
これを知った時、理想のマイペースというのはこういう状態なのかもしれないと思いました。自分のペース(つまり利己)で生きていることが、いつの間にか誰かのためになっている(つまり利他)ような状態だと、お互いにとってプラスになるし、誰からも咎[とが]められることもない…これなら、持続可能だし、自分も気分よくマイペースでいられると思ったのです。
もちろんあくまで理想の状態なので、必ずしも達成できるとは思ってないのですが、目指すべき状態としてはこういう状態がよいのではないかと今のところ考えています。
なので最近は支援の中でもこの考え方を少し取り入れて、例えば成人の発達障害の方が、なるべく自分のペースを崩さずにでも周りの人にとっても役に立つような仕事の仕方はないだろうかと考えたり、不登校のお子さんが自宅で過ごす際に、本人にとっても家族にとってもほどよい家での過ごし方などを考えたりしています。
そう考えると、僕の今までの支援というのは少し偏りがあったかなと思っていて、つい、支援の対象となっている人に目が行きがちで、その人のために回りが合わせるべき、変わるべきと考えがちだったなぁと思いました。
だれにでもマイペースがあるので、変に二項対立にならないよう、それぞれのマイペースが尊重されるようなアプローチを心がけたいと今は考えています。
ただ、なかなか難しいんですよねぇ…まだまだシナジーが発揮される状況を作るのは模索中で、そもそもそれが良いのかというのもこれからの実践の中でより精査していくことが大切かなと思っています。
いろいろと試してみた結果についてはこれからまた皆さんにも共有していければと思っています。