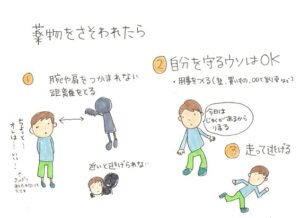精神科で長年働いてきた看護師のチアキが、精神科の受診や治療などの質問に回答するコーナーです。
質問タイトル:医療受診に保護者の理解が得られないケースについて
養護教諭です。
(強迫と思われる症状があって)受診が必要な状態だと思いますが、保護者の理解が得られなくて、なかなか医療機関につながりません。学校でも工夫をしていますが、環境調整だけでどうにもならないこともあります。一番苦しいのは子ども自身ではないかと思っています。どんな糸口がありますか。
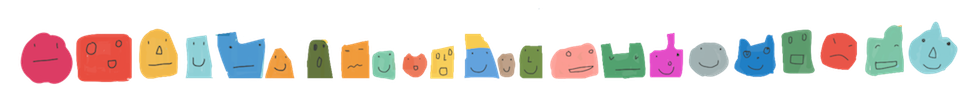
チアキの回答
ご質問ありがとうございます。
先生の心配が目に浮かぶかなあと思いながら読みました。
(強迫)症状の出方が、場所によってちがうということはよくあります。学校での様子と、家庭での様子がちがっていて、もしかしたら、家庭ではそこまで困っていないのかもしれません。病院に行く行かないではなく、「学校の様子と家庭での様子の意見交換ができること」を最初の目標にできるとよいと思います。
「病院に行かせない親」という視点は、頭から外してもらって、親御さんなりになにかを心配して、病院受診をできないのかもしれない…という視点で考えてみます。
例えば、子どもに薬を飲ませるのは心配…とか、もう少し様子を見てみたいとか、以前、家で病院の話を子どもにしたらケンカになったとか、家族や親せきの中でだれかの精神科にネガティブな強い意見があるとか…
家族の想いも大切に話せたらいいなと思います。
本人の意向をすっ飛ばさないことも大切です。
子どもの年れいが思春期前なのか、子ども自身が語れる年れいなのか、といったことにもよりますが、子ども自身がそのことで困っているのであれば
どんなことで困ってるのか
学校や、家で、どう生活したいか
今のままでいいと思っているのか
しんどいとか、症状がなくなったらいいと思ってるのか
子どもも病院に行ってみたいと思ってるのか
などについて、関係のできている先生と話せるといいなと思います。
子どもは受診したいのに、親が同意しないという場合。
以前、強迫症状ではありませんが、かかわりのあった子どもでこのような例がありました。
子ども自身は「周囲の目がこわい、悪口を言われている気がする」ととても周囲に過敏で、自傷もあって、受診の必要がある状態だと思われました。
本人も、少しでも今のつらさが楽になる可能性があるならと同意していましたが、親御さんは気持ちの問題と全く話が通じない状態でした。
このときは、親御さんのこれまでの歩みや工夫を共有し、想いを丁寧聞いていくなかで、「睡眠や食事がとれない」ことについては、親御さんも気にしていることがわかりました。そこを切り口に、半年以上かかりましたが、受診につながることができました。
子ども本人と作戦会議をしながら、家族にどう伝えるか、「伝わることば」を一緒に探ったケースです。
強迫症状(や多くの精神科の症状)は、お薬を少し飲んだからといって、すぐに症状がぴたっとなくなるかはわかりません。むしろそういうことはあまりなくて、ちょっぴり楽になるかも…くらいの期待度で、医療を考えておけるといいかなと思います。
無理強いしても、一回の受診でなんとかなることではないので、丁寧、丁寧にやることが大切なのかなと思います。

チアキ
関西→関東、精神科ひとすじの看護師。
ぷるすあるはの制作担当、絵本ではお話と絵を担当しています。