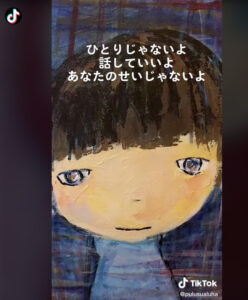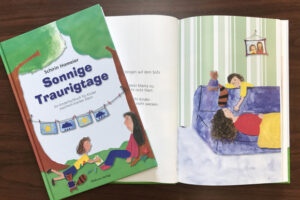おがてぃです。
ここ2-3年の話なのですが、本業でも副業でも「対話」の重要性について伝える機会が増えているように感じます。これは合理的配慮[はいりょ]の時もそうだし、親子の関係の時もそうだし、職場環境の改善の時もそうで、人と人とがかかわる際には「対話」ということがより意識[いしき]して求められるようになってきたのだと感じています。
「対話」が注目されるようになったのは、自分の体感だと10年くらい前からの話で、やはりオープン・ダイアローグの影響が大きいと思っています。僕が初めてオープンダイアローグに出会ったのは、まだ行政で働いていた時で、もともと噂[うわさ]レベルで何となく知っていたのを、心理職の勉強会に先生をお招きしてお話を伺い、これはもっと広めていった方が良いことだなぁと感じました。
ただ一方で、フィンランドで実践されている精神医療的[せいしんいりょうてき]な仕組み(連絡が来たら24時間以内に訪問する、複数名で対応したり、治療方針を本人の同席で決定するなど)はあまりにも日本とちがいがあったので、かなり戦略的にやらないとなかなか普及[ふきゅう]していかないのではないかと思いました。
その後、職場も変わってもう少し柔軟[じゅうなん]に考えて、まずは「対話」をちょっとでも意識して人と関わることから始めていければよいかなと思い、職場の人や相談に来られた方と対話的に話を進めることを意識してきました。
オープンダイアローグの形式だと複数人集まって進めることが大事で、リフレクティング(当事者の前で複数の支援者が感想やアイデアなどを話し合い、それを当事者にきいていてもらって、後で感想を述べたりする手法)などをするのですが、やはり人数などがそろわない場合もあり、その時は1対1であっても少しでも対話的になるように工夫を考えたりしています。
さて、そのような「対話」ですが、マイペースについて考えていく時もやはり大事なことだと思っております。
最近やっていることとしては、はじめに「ここのところマイペースに過ごせたと感じたときはいつですか?」と伺い、いろいろとお話を伺ってからリフレクティングで感想を伝えたり、1対1の時はひとり言的に感じたことなどを伝えて、それを聞いてどう思ったかという感想を伺っています。
これが普通の相談や会話と何がちがうのかというと「話が押しつけがましくない」というところがあります。通常の話の進め方だとマイペースに過ごしたことについて、あれこれとアドバイスをしてしまうことが多く、なんとなく相手のマイペースを操作してしまって、相手のマイペースを疎外[そがい]してしまうような感じがしていました。とくに支援者として被支援者に関わるという場合はどうしてもパワーバランス的に支援者側の方が強くなってしまうので、なおさらそう感じていました。
本来その人のペースはその人にしかわからないので(本人すらわかっていない時もありますが…)、そちらを優先すべきなのですが、支援者側から「もっとこうした方が良い」と伝えると相手側も「そうした方が良いのかも…」と思って、自分のペースが操作[そうさ]されてしまうことがあります。
もちろん本人が納得して「そうした方が良い」と思って変えるならそれはそれでよいのですが、なんというか鵜呑[うの]みにしてしまうというか
「自分は果たしてどうしたいんだろう…」
というワンクッション置いた内省[ないせい]が無いままにそうなってしまうのはマイペースな進め方ではないなぁと感じています。
なので、リフレクティングを用いて、少し本人に内省してもらう間をつくるというのが、マイペースに相談を進めるうえで大切だなと思っています。
***
1対1の場合は、先ほど伝えたように「ちょっとこれから僕の感じたことや思ったことをまとめてみますので、その場で聴いていてもらってもよいですか?」と相手に伝え、ちょっと目線をそらしてひとり言のようにつぶやいて、その後で感想をきいたりしています。
***
工夫としてはほかにもいくつかあるのですが、オープンダイアローグでの対話は「話すこと」と「きくこと」を分けるということが大事だときいたことがあるので、きく時はきくことに徹[てっ]し、話すときは話すことをするという順番が上手く作れるとよいのだろうと思っています。
今回はマイペースの内容というよりは相談をマイペースに進めるための工夫として「対話」が重要であるということをお伝えしました。これは相手の「自己選択」や「自己決定」を尊重するためにも大事な点かなぁと思っているので、今後も色々と工夫を考えていきたいと思っています。