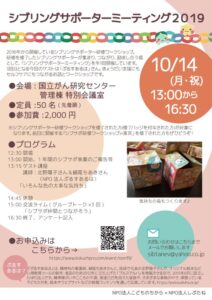ゆるゆる子育てを担当している公認心理師・臨床心理士おがてぃが、子育ての相談に回答するコーナーです。
質問タイトル:場面緘黙
年れい: 〜就学前
質問内容
娘は幼稚園の年少クラスで今年4月に入園しました。
入園から1ヶ月以上たちますが園では一言も話さず飲食もできていません。
園にいる間は体が固まり自然に動くことができなくなります。
なので活動にもほとんど参加できていません。
お家では着替えなど自分でできることも増えているのですが、幼稚園に行くとサポートではなく全介助している状態ですと言われました。
娘自身も幼稚園に行くとなぜかいつも出来ることも出来ない…と言っていました。
お家では幼稚園のことなどたくさん話してくれたり、ひたすら幼稚園ごっこをしたがります。
自分はこんなはずじゃない…と言わんばかりに幼稚園ごっこを何度もする娘が健気で切なくも思えます。
園の先生や市の発達相談に相談してみましたが様子を見ましょうと言われました。
私なりにたくさん調べ、場面緘黙という名前にたどり着きました。
娘に診断名をつけたいわけではないのですが、何か抱えているなら少しでも早くケアしてあげたいと思っています。
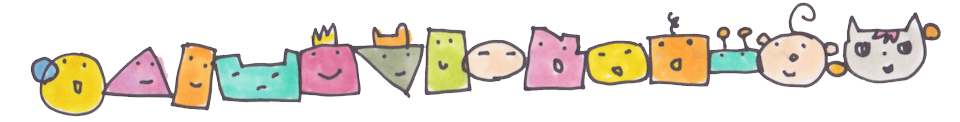
おがてぃの回答
ご相談いただきありがとうございます。
お子さんが幼稚園ではお話しできず、自然に動くことができないとのことで、相談者さんが心配なさるのも無理もないことかと思いました。今回は場面緘黙ではないかということとケアの仕方について相談したいという趣旨だと理解しましたので、その点についてお伝えできればと思います。
まず「場面緘黙」とは何なのかという話からしますと、精神科での診断などに用いられるDSMなどを参考に考えると「家などでは普通に話すことができるが、園や学校などの特定の場面で、1か月以上声を出して話すことができない状態が続くこと」という定義になります。
他の病気やいわゆる発達障害などの影響ある場合はそちらの診断が主となることが多いのですが、そうでない場合は「場面緘黙」と診断がつけられることがあります。
今回のお子さんの場合、他の病気や障害などがあるかどうかは相談内容からはわからなかったのですが、少なくとも場面緘黙に当てはまるような症状があるとは言えるのではないかと思いました。もし、場面緘黙の症状に当てはまるかどうか改めて気になるようであれば、下記のサイトなどを参考にしてもらえればと思います。
》NHKハートネット 場面緘黙とは 基礎情報・支援情報
》かんもくネット 場面緘黙とは
場面緘黙の発症要因は生来の気質や神経発達、環境要因など複数のことが影響しあって生じるとされており、はっきりとしたことはわかっていません。ただ、「不安になりやすい気質」が関連している可能性があるとされており、僕も今までお会いしたことのある場面緘黙のお子さまも不安の強いお子さんがそれなりにいました。
ただ、過去に場面緘黙だったという成人の方とお話しした際には「しゃべってやるもんかと思って黙っていた」とも言っていたので、いろいろと理由は複雑なのかもしれません。
家族ができるサポートとしては、まずは家庭内ではよくお話ができているということなので、その点を大切にしていただくことが大事かなと思いました。それはお家では安心して過ごせているということだと思うので、外で不安なことがあったとしてもお家でゆっくり休んで回復することができるということだからです。
また、今回の相談者さんから教えてもらったことで幼稚園ごっこをするとありましたが、それは安心な環境の場で振り返りをしたり、リハーサルをしたりしながら自分の中での不安を解消しようとしているのかもしれないなと思いました。もしそうであれば家庭内という安心な場だからこそできることなので、基本的には見守ってあげて、時々辛そうなら次に幼稚園でどうすればよいかを教えてあげられるとよいかと思いました。
場面緘黙を直すためにお家以外でしゃべれるようにしていくアプローチは、基本的にはスモールステップでの取り組みになります。無理に不安や緊張の強い場面で話させるのではなく、ちょっとずつ慣れていってもらうことが大事なので、どの場面でどのくらい話せるのかを改めて観察し、お子さんにとってちょうどよいステップを考えられるとよいかと思いました。その際、園以外の外出先や習い事では話せるか、園以外の場所でお友達や他の大人と話せるのかということも観察してみて、ちょっとずつ話せる範囲や機会が増えるということをイメージしてもらえるとよいのではないかと思いました。
ただ、こういったスモールステップを作ったり、園の先生に協力をお願いしたりを相談者さん一人でするのはけっこう大変なので、どこかに相談しながらできるとよいのではないかと思っています。園や発達相談からは様子をみましょうと言われたそうですが、ご心配なら相談先としてはお住まいの地域にある保健センターや子ども家庭センター、医療機関などに改めて相談しに行ってもよいかと思いました。もし、発達障害などの可能性も気になるということであれば、児童発達支援センター等でもよいかもしれません。
上記でスモールステップで取り組むとお伝えしたのですが、実はそのことについて相談者さんに伝えるべきかどうか、ちょっと悩みました。なぜかというとスモールステップで取り組むとお伝えすると割と気持ちが焦ってしまい、お家でいろいろとやらせたくなってしまう方がいて、その結果としてお家が安心できる場でなくなってしまうことがあるからです。
お家で安心できることがお子さんにとっては何より大事なことだと思うので、取り組むとしてもなるべく無理なく、ゆるゆるとやってもらえるとよいなぁと思います。

おがてぃ
普段は民間企業で心理職として仕事をしています、3児の父です。
公認心理師。臨床心理士。
毎月のメールマガジン「アルハ通信」で最新情報が届きます
サイト運営団体:NPO法人ぷるすあるは
》これまでのメールマガジンをみる