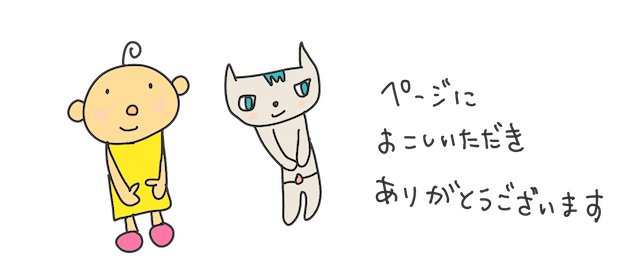
ページにお越しいただきありがとうございます。
精神疾患、精神障がいをかかえたときなど…メンタルヘルス関連の社会福祉サービスの中で、特に、経済的な支援についてまとめました。
注)実際の制度は複雑なことも多いです。このページでは読みやすいように簡略化しています。
代表的なものをあげていますが、ほかにさまざまな制度があります。
更新:2025年11月
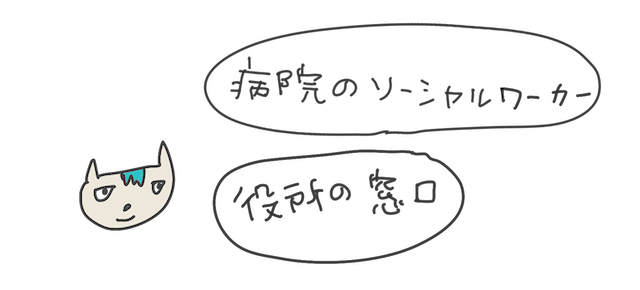
支援者の方へのお願い
情報提供する場合は、お住まいの自治体の制度を事前に問い合わせて、利用者の方が対象になることを確認してからお伝えください。申請窓口への同行や、書類の記入サポートなど、いっしょに取り組んでくださるととても心強いです。

1 医療費[いりょうひ]にかんする制度
自立支援医療[じりつ しえん いりょう] …通院費・薬代
精神疾患で継続的に通院するときの医療費・薬代の自己負担が3割→1割になります。
経済的な負担が小さくなり、通院をつづけやすくなりますが、意外と制度が知られていません。医師の診断書などが必要になります。主治医、病院のケースワーカー、受付の人など、話しやすい人に聞いてみます。
申請時に、医療機関、薬局をそれぞれ一ヶ所登録します。登録した機関での支払いが1割になります。デイケア・訪問看護の利用料にも適応されます(登録要)。毎年の更新が必要です。
所得によって、一ヶ月あたりの医療費の上限が決まっています→1割よりも安いこともあります。
一定の所得をこえるときには使えません。
高額療養費制度[こうがく りょうようひ] …入院費など
入院のときなど、高い医療費がかかるとき、自己負担の上限があります。後日、上限をこえてはらったお金がかえってきます。事前に申請することで、窓口の支払いを上限額にすることができます。病院のソーシャルワーカーに相談します。
有効期間(最長1年)内であれば、入院の度に申請する必要はありません。
※マイナンバーカードを健康保険証として使うと、病院によっては「支払いを上限にするための手続き」がいらない場合があります。くわしくは、入っている健康保険(国保・協会けんぽ・職場の健康保険など)の案内を見てください。
保険証がない(保険に入っていない、未納がつづいて切れてしまった)とき、お金がないときの受診について
「無料低額診療事業*」を行なっている病院を探します。
[住んでいる都道府県 無料低額診療事業] で検索
→例えば、埼玉県であれば、38ヶ所の病院がでてきます(2021.7時点)
》[埼玉 無料低額診療事業]
*生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料又は低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号の規定に基づく第二種社会福祉事業)
2 仕事・労働にかんする制度
会社の窓口・相談先(総務課・人事労務担当・カウンセリング室など)があれば会社で相談してみます。
そのほか、それぞれの制度の窓口は<>に記載しています。
傷病手当金[しょうびょう てあて] …休職中
休業(病休)中、給料の約2/3相当が、休業4日目から、最長1年6ヶ月の範囲で支給されます。
書類に、医師、事業主の記入が必要になります。
<健康保険協会の都道府県支部/健康保険組合(勤務先に総務担当がある場合は、申請を代行してくれます)>
健康保険・共済組合の人が対象です。国民健康保険の人にはこの制度はありません。
くわしい情報 》全国健康保険協会>病気やケガで会社を休んだとき
雇用保険(いわゆる失業保険) …退職後
退職後(失業・求職中)の保障です。
退職までの2年間で、12ヶ月以上雇用保険に加入している人が対象です(倒産や解雇などは、1年間に最低6ヶ月加入です。細かい条件は個別に確認します)。
会社の都合での退職か自己の都合か、勤務期間によって、受けられる日数(90日—330日)、給付率(給料の5-8割程度)が変わります。
<ハローワーク>
労災(労働災害)について
病気になった責任が、明らかに、労働条件によるものと考えられるときは、労災の申請ができます。
<労働基準監察署>
退職後の保険・年金について
退職すると、これまでの職場の健康保険(病院にかかるときの保険)と年金がなくなるので、手続きが必要になります。
職場勤めのときは、職場が、従業員にかわって、給料から天引きして支払っています。
保険
退職後は、国民健康保険になりますが、元勤務先の健康保険を、2年間継続することができます。「任意継続」の制度で、退職後20日以内に手続きが必要です。
<お住まいの協会けんぽ支部>
》任意継続の加入手続きについて 全国健康保険協会のページへ
年金
職場でかけるのが「厚生年金(会社員・公務員など)*」
自営業の人や学生、仕事をしていない人がかけるのが「国民年金」です。
退職すると、国民年金になりますが、保険料、年金の支払いがむずかしい場合は、免除・減免(へらす)の申請をします。
未納[みのう]だと、将来の年金の受け取りや、障害年金の申請への影響などがあります。
<役所の国民年金担当窓口>
》保険料を納めることが、経済的に難しいとき 日本年金機構のページへ
*以前は、公務員や私立学校教職員が加入する公的年金制度は「共済年金」と呼ばれていましたが、被用者の年金制度の一元化により、現在は厚生年金保険に加入しています。
3 生活費にかんする制度
障害年金
病気やケガなどが原因で、障害が継続する場合に、生活を保障する制度です。初診から1年6ヶ月以上たっていて、障害が一定の重さであるときに申請できます。手続きや受給の条件がとても複雑で、申請にはエネルギーが必要です。病院のケースワーカーに相談してみます。
生活保護
病気や障害、高齢などで働くことがむずかしかったり、経済的に困ったときに、生活を保障する制度です。
個人ではなく「世帯単位」が対象の制度です。
役所が窓口になりますが、手続きや書類が複雑なので、病院のケースワーカーなどにまず相談できるとよいと思います。
》生活保護制度 厚生労働省のページ
》知っていますか?生活保護のこと〜生活保護制度の正しい理解と活用のために〜 生活保護に関する日本弁護士連合会のパンフレット
》路上からもできるわたしの生活保護申請ガイド2017年版|ホームレス総合相談ネットワーク(120ページにおよぶ、とてもくわしいガイドです。「福祉事務所で申請するときこう言われたらこう言おう」など実践[じっせい]的な内容もあります。)
生活にお困りの方へ|認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい)
生活困窮[こんきゅう]者 自立支援制度
「自立相談支援事業」を中心に、生活全般にわたるこまりごとについて、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄りそいながら、ほかの専門機関とも連携して、解決に向けた支援を行います。
「家計相談事業」は家計状況を見える化して課題に気づき、相談者が自分で家計を管理できるように支援します。
また、住居をもたない方に、一定期間、衣食住を提供する「一時生活支援事業」、離職[りしょく]などにより住居を失った方などへ、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給する「住居確保給付金の支給」、「子どもの学習支援」などがあります。
》生活困窮者自立支援制度とは|困窮者支援情報共有サイト
》全国の自立相談支援機関・窓口一覧
そのほか
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当
- 生活福祉資金 など
4 手帳(精神障害者保健福祉手帳)で受けられる経済的支援
手帳は、初診から6ヶ月以上たった日から申請できます。
手帳があることで、税金(所得税、住民税ほか)、携帯の基本料、NHK受信料、公共交通機関、公共施設の利用料…など、さまざまな割引の適応になることがあります。
手帳を受け取るときに、利用できるサービスの案内をもらえる(郵送なら同封されている)と思います。市町村によって、さまざまなサービスがありますので、使えそうなサービスと利用方法を確認します。
手帳をその場でみせれば割引されるものもあれば、申請が必要なものもあります。
無料サービスや割引のある施設の情報や、その他障がい者への減免[げんめん]制度(お金の負担を軽くするしくみ)などをまとめて発信している情報サイトです。都道府県別に情報まとまっています。
書類の更新期限を知らせてくれるサービス
『つたえる日記』無料アプリ
受診時に伝えることや言われたこと、日々の体調メモできるコミュニケーション&体調管理アプリ。「自立支援医療(精神通院医療)、精神保健福祉手帳、障害年金」を登録しておくと、通知がでる機能があります。ユーザー登録なしで使えます。
》アプリ紹介のページへ(制作元のエルワイスのHPへ)
東京都・LINEによる通知サービス
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方に対し、更新手続き開始1週間前にLINEにより通知するサービスです。名前や連絡先、住所の登録は不要です。
》東京都のページへ
》子どもと家族をささえる社会保障制度やサービスのページへ戻る
制度やサービスの利用にむけて、相談できるところの情報、参考サイトや本を紹介しています





